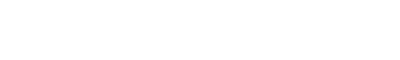2025.09.04
腸活について

はじめに
腸は私たちの健康を支える重要な臓器であり、消化吸収だけでなく、免疫機能、代謝、さらには精神的な健康にも深く関与しています。人間の腸内には約1000種類、100兆個もの細菌が生息しており、これを「腸内フローラ」または「腸内マイクロバイオーム」と呼びます。この細菌叢のバランスが崩れると、肥満、糖尿病、心血管疾患、うつ病、アレルギー、自己免疫疾患などのリスクが高まることが科学的に示されています。1)
「腸活」とは、食事や生活習慣を通じて腸内細菌叢を最適化し、健康を維持・向上させる活動を指します。本コラムでは、科学的根拠に基づいた腸活の実践方法とその効果を詳細に解説し、日本の食文化との関連についても掘り下げます。
腸内細菌叢は、食物の消化吸収を助けるだけでなく、ビタミンや短鎖脂肪酸の生成、免疫系の調節、神経伝達物質の産生にも関与します。近年、腸内細菌叢とメンタルヘルスの関連性が注目されており、ストレスや不安、うつ病の症状が腸内環境の乱れと関連していることが報告されています。このような背景から、腸活は単なる健康維持の手段を超え、総合的なウェルビーイング(心身だけでなく、社会的な面も含め満たされた状態)を追求するための重要なアプローチとして認識されています。
本コラムでは、腸活の科学的根拠をさらに深掘りし、食物繊維、プロバイオティクス、プレバイオティクスといった主要な要素の解説に加え、運動、睡眠、ストレス管理といった生活習慣が腸内環境に与える影響についても解説します。また、日本独自の食文化がどのように腸活に寄与するのか、現代日本人における具体的な食事例や提示します。さらに、腸活を日常生活に取り入れるための具体的な方法について提示します。
腸活の科学的根拠
腸内細菌叢は、食事や生活習慣によって大きく影響を受けます。以下では、腸活の主要な方法や、それを裏付ける科学的証拠を詳しく説明します。さらに、腸内細菌叢の多様性が健康に与える影響や、最新の研究に基づく新たな知見についても解説します。
1. プロバイオティクスの摂取
プロバイオティクスとは、腸内環境を整える生きた善玉菌を含む食品やサプリメントのことをいいます。ヨーグルトや発酵食品に多く含まれ、乳酸菌やビフィズス菌が代表的で、広く食品として販売もされています。腸内フローラのバランスを改善し、消化や免疫をサポートし健康へと関与します。2018年研究では、プロバイオティクス(主にビフィズス菌やラクトバチルス属)摂取が下痢、壊死性腸炎、急性上気道感染症、嚢胞性線維症の肺増悪、小児の湿疹の予防に有効であることが確認されました。2)
また、2型糖尿病患者において、代謝機能の改善や炎症マーカーの改善にも効果があることが示唆されています。プロバイオティクスは、腸内細菌叢のバランスを改善し、免疫調節や短鎖脂肪酸など腸内での生成を通じて健康を促進します。
プロバイオティクスの摂取方法には、サプリメントと発酵食品がありますが、サプリメントは腸内に定着しない可能性があるため、ヨーグルト、ケフィア、キムチ、納豆などの発酵食品からの摂取が推奨されます。たとえば、納豆に含まれる納豆菌は、腸内で有益な細菌の増殖を助けることが証明されています。個人ごとの食生活や腸内細菌叢の特性に応じたプロバイオティクスの選択が効果を最大化する鍵となります。たとえば、ビフィズス菌ロンガムといわれるプロバイオティクスにおいて腸への定着は、個人の腸内環境に依存することが報告されています。
さらに、プロバイオティクスは食物繊維と同様に神経伝達物質の産生に影響を与え、うつ病や不安障害の症状を軽減する可能性があります。研究では、ラクトバチルスやビフィズス菌がセロトニンやGABAの生成を促進し、ストレス応答を抑制することが示唆されています。3) このような効果は、腸活がメンタルヘルスにも寄与する可能性を示しています。
2. プレバイオティクス食品
プレバイオティクスは、腸内の有益な細菌を選択的に増やす非消化性の食物成分です。代表的なものだと食物繊維やオリゴ糖が有名です。食物繊維では難消化デキストリン、ポリデキストロース、イヌリンなどがこれに含まれます。またオリゴ糖では、フルクトオリゴ糖(、ガラクトオリゴ糖、ラクツロース、などが知られており、これらはビフィズス菌やラクトバチルスなどの増殖を促進します。これにより、短鎖脂肪酸の生成が増加し、前述のように腸のバリア機能が強化され、肥満や心代謝疾患のリスクが低減します。たとえば、10g/日のフルクトオリゴ糖の摂取は12週間で1.03kgの体重減少を促進し、8g/日のイヌリン摂取は青少年の骨密度を向上させることが報告されています。
プレバイオティクスは、ニンニク、タマネギ、バナナ、アスパラガス、こんにゃくなどに豊富に含まれており、日常的に摂取することで腸内環境を改善できます。プレバイオティクスの効果は、腸内細菌の酵素能力や炭水化物の構造に依存するため、個人差がある点に注意が必要です。4) また、プレバイオティクスは免疫系の調節にも寄与し、アレルギー反応を抑える効果があることが報告されています。
3. 食物繊維の摂取
食物繊維とは、プレバイオティクスに含まれ、人の消化酵素で消化されない食物中の成分の総称です。日常生活でよく耳にする一般的な言葉ですが、食物繊維摂取が持つ健康への有効性は認知されてないことが方が多いです。人の消化酵素で分解されないため、糖や脂質、タンパク質と異なりエネルギー源にはなりませんが、整腸作用や血糖値の上昇を抑えるなど、便通の改善に留まらず様々な健康への効果を持っています。
食物繊維は腸内細菌によって発酵され、短鎖脂肪酸である酢酸、プロピオン酸、酪酸を生成します。これら短鎖脂肪酸は、腸の粘膜バリアを強化し、炎症を抑え、代謝を改善します。研究では、食物繊維の摂取が心血管疾患のリスクを低減し、腸の健康を促進することが示されています。4) 具体的には、食物繊維は血性LDLコレステロールを低下させ、便の量を増やして排便を促進します。たとえば、1日あたり14gの食物繊維摂取(1000kcalあたり)は、心血管疾患リスクの低減に関連していることが研究で報告されています。また、食物繊維の摂取量が15g/日以上の場合、2型糖尿病のリスクが低下することが報告されています。4)
食物繊維には、可溶性と不溶性の2種類があります。可溶性食物繊維は水に溶け、ゲル状の物質を形成し、消化を遅らせて血糖値の急上昇を抑えます。オートミール、りんご、豆類などに多く含まれます。不溶性食物繊維は水に溶けず、便の量を増やして便秘を予防します。全粒穀物、野菜、ナッツなどに豊富です。両方の種類をバランスよく摂取することで、腸内細菌の多様性を高め、有益な細菌の増殖を促進します。例として、100gの炭水化物が発酵するごとに約30gの細菌量が増加し、便の体積が増すことが知られています。
さらに、食物繊維は脳にも影響を与え、ストレス応答の軽減や気分・認知機能の改善に寄与する可能性が報告されています。食物繊維が豊富な食事は、短鎖脂肪酸の生成を通じて炎症物質の産生を抑えることで神経系に作用し、メンタルヘルスをサポートするというメカニズムが想定されています。このように、食物繊維は身体的・精神的健康の両方に貢献する重要な栄養素といわれています。
4. バランスの取れた多様な食事
多様な食事は、腸内細菌の多様性を高め、健康を促進します。野菜、果物、全粒穀物、豆類、ナッツ、魚介類、オリーブオイルなどを中心に摂取し、赤身の肉や乳製品を適度に制限する地中海式食事法 いんついて研究では、地中海式食事法を取り入れる人は、有益な細菌(ビフィドバクテリウム、フェカリバクテリウム、ロゼブリアなど)が多く、短鎖脂肪酸の血中濃度が高いことが示されました。5)逆に、地中海式食事法とは離れた食生活をした場合、尿中のトリメチルアミンオキシド(血中濃度上昇が、心血管疾患のリスク増加と関連することが示唆されている物質)が上昇し、心血管疾患のリスクが高まる可能性があります。
地中海式食事法は、植物性食品や不飽和脂肪酸、ポリフェノールの摂取を通じて、腸内細菌の多様性を高め、炎症を抑えます。この食事法は日本でも取り入れやすく、野菜や魚介類を中心とした食事を意識することで腸活に役立ちます。たとえば、日本は海洋資源に富んだ地理をしており青魚、果物野菜、オリーブオイルを使った料理は、地中海式食事法の要素を取り入れつつ、日本の現代の食文化にも適合します。
5. 有害物質の回避
加工食品、人工甘味料(スクラロース、アスパルテーム、サッカリンなど)、食品添加物(カルボキシメチルセルロース、ポリソルベート80)、抗生物質の過剰使用は、腸内細菌叢のバランスを崩す可能性を指摘されています。これらが腸内細菌の多様性を低下させ、炎症を促進することを指摘しています。2) たとえば、人工甘味料は腸内細菌の組成を変化させ、グルコース不耐性を引き起こす可能性があります。乳化剤は腸のバリア機能を損ない、炎症を促進するプロテオバクテリアを増加させます。
これらの有害物質を避けるためには、加工食品やファストフード摂取を控え、天然食材を選ぶことが重要です。抗生物質は医師の指導のもとで適切に使用し、人工甘味料の代わりに蜂蜜やメープルシロップなどの天然甘味料を選ぶことが推奨されます。
6. 運動と腸内細菌叢
運動は腸内細菌叢の多様性を高め、短鎖脂肪酸を生成する細菌を増加させます。定期的な運動は腸の蠕動運動を促進し、便秘を予防します。たとえば、週に150分の中程度の有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)は、腸内環境の改善に役立つことが研究されています。運動はストレス軽減にも寄与し、脳腸相関を通じて腸内細菌に良い影響を与えます。過敏性腸症候群などの症状改善にも運動の効果が立証されています。
7. 睡眠とストレス管理
睡眠不足や睡眠の質の低下は、腸内細菌叢のバランスを崩す要因となり、腸内細菌叢の多様性や組成に影響を与えることが報告されています。具体的なメカニズムとして睡眠不足は、交感神経系の活性化やコルチゾール血中濃度の上昇を引き起こし、腸のバリア機能を損なうことが示唆されています。これにより、腸内細菌の異常増殖や有害な代謝産物(例:リポ多糖類、LPS)の血中移行が促進されることで、腸内細菌叢のバランスが崩れることがいわれています。
睡眠と腸内細菌叢の関連について研究した報告では、短期間の睡眠制限(4時間睡眠を2晩)が、健常な若年男性の腸内細菌叢の組成を変化させ、健康への有用性が示されている細菌の比率が低下したことを報告しています。6)
良質な睡眠(7~8時間/日)は、腸と脳のコミュニケーションを正常に保ち、ストレス応答を抑制します。ストレス管理には、瞑想、深呼吸、ヨガなどのリラクゼーション法が効果的で、腸内環境の改善に寄与するため取り入れるようにしましょう。
日本の研究と腸活
日本は腸内細菌研究の先進国であり、独自の食文化が腸内細菌叢に影響を与えています。2016年の研究では、日本人の腸内細菌叢はビフィズス菌が豊富であり、納豆、味噌、漬物、海藻、根菜類などの日本の伝統食に関連している可能性が示されました。6)
ビフィズス菌は腸のバリア機能を強化し、免疫系を調節し、日本人の低BMIや長寿に寄与している可能性があります。
2021年の大規模コホート研究(共通の特性を持つ集団を追跡し、時間経過に伴う健康状態の変化や疾病の発生状況を調べる疫学研究)では、日本人の腸内細菌叢の多様性と、食事や生活習慣との関連が分析されました。8) たとえば、排便頻度、性別、年齢、ビール摂取などが腸内細菌組成に影響を与えることが確認されました。これらの結果は、個々の生活習慣を考慮した腸活の重要性を示しています。
日本の食文化は、発酵食品や食物繊維が豊富な食材を提供します。納豆はビフィズス菌を増やし、味噌や漬物はプロバイオティクス源として優れています。昆布、わかめ、ごぼうなどはプレバイオティクスとして機能し、腸内環境を改善します。また、緑茶や大豆製品に含まれるポリフェノールは、腸内細菌叢を改善し、炎症を抑える効果があります。2)
現代日本では食生活の欧米化に伴い、自己免疫性腸炎や大腸ポリープの発生率が上昇傾向にあるといわれています。現代社会では、食生活を古き良き日本食へシフトすることで、将来の疾病リスクの低下や、精神状態の安定などに寄与するかもしれません。
腸活の実践方法

以下では、腸活を日常生活に取り入れるための具体的な実践方法を紹介します。これらの方法は、科学的根拠に基づいており、日本の食文化やライフスタイルに適応しやすい形で提案します。
1. 食物繊維を豊富に摂る
- 推奨食品: りんご、バナナ、ブロッコリー、にんじん、玄米、オートミール、大豆、レンズ豆、アーモンド、チアシード、ごぼう、さつまいも。
- 効果: 腸内細菌のエサとなり、短鎖脂肪酸の生成を促進。腸のバリア機能を強化し、炎症を抑える。1日あたり25~30gの摂取が理想的。
- 実践例: 朝食にオートミールとバナナ、昼食に玄米と野菜のスープ、夕食に豆類のサラダやごぼうのきんぴらを取り入れる。間食にアーモンドやチアシードを加えたヨーグルトを食べる。
2. プロバイオティクスを摂取する
- 推奨食品: ヨーグルト、ケフィア、ザワークラウト、キムチ、納豆、味噌、漬物。
- 効果: 有益な微生物を補充し、消化器系の健康をサポート。免疫機能の向上や炎症の軽減。
- 実践例: 毎朝、プレーンヨーグルトにフルーツをトッピング、または夕食に味噌汁や納豆を食べる。週に数回、キムチや漬物を副菜として取り入れる。
3. プレバイオティクス食品を食べる
- 推奨食品: ニンニク、タマネギ、バナナ、アスパラガス、チコリ根、こんにゃく。
- 効果: 有益な細菌の増殖を促進し、短鎖脂肪酸の生成を増加。腸の健康を維持。
- 実践例: サラダにタマネギやアスパラガスを加え、スープにニンニクを活用。こんにゃくを使った煮物や炒め物を週に数回取り入れる。
4. バランスの取れた食事を心がける
- 地中海式食事法: 野菜、果物、全粒穀物、オリーブオイル、魚介類を多く摂取。肉類や乳製品の適度な制限。
- 効果: 腸内細菌の多様性を高め、炎症を抑え、心血管疾患リスクを低減。
- 実践例: 週に数回、サーモンや青魚(サバなど)を使った料理や、オリーブオイルで調理した野菜を取り入れる。緑茶や豆腐を使った料理も積極的に活用。
5. 有害物質を避ける
- 避けるべきもの: 加工食品(スナック菓子、インスタント食品)、人工甘味料、過剰な抗生物質。
- 効果: 腸内細菌叢のバランスを保護し、炎症を防ぐ。
- 実践例: 加工食品の代わりに新鮮な食材を選び、飲料は無糖のものを選ぶ。抗生物質は医師の指導のもとで使用。
6. 運動習慣を取り入れる
- 推奨活動: ウォーキング、サイクリング、ヨガ、ピラティス。
- 効果: 腸内細菌の多様性を高め、便秘を予防。ストレス軽減にも寄与。
- 実践例: 週に3~4回、30分のウォーキングやヨガを行い、腸の蠕動運動を促進する。週合計で150分程度の運動が理想的。
7. 睡眠とストレス管理
- 推奨習慣: 7~8時間の睡眠、瞑想、深呼吸。
- 効果: ホルモンバランスを整えることで腸内細菌叢のバランスを保つ。
- 実践例: 就寝前にスマートフォンやPCの使用を控え、瞑想や深呼吸でリラックスする時間を確保。意識して7時間前後の睡眠時間をとるようにする。
日本の食文化と腸活
日本の伝統的な食文化は、腸活に最適な食材を提供します。納豆はビフィズス菌を増やす効果があり、味噌や漬物はプロバイオティクス源として優れています。昆布やわかめなどの海藻、根菜類、ごぼうなどは食物繊維が豊富で、プレバイオティクスとしても機能します。N前述した日本人の腸内細菌叢についての研究では、日本人の腸内細菌叢がビフィズス菌に富むことが確認され、これが日本の低BMIや長寿に関連している可能性が示唆されています。7) ビール摂取などの生活習慣が腸内細菌組成に影響を与えることが明らかになり、日常的な注意が重要であると強調されています。食生活が多様化し、国内での世界各国の食事へのアクセスや、加工食品が多くなった今こそ、日本食文化の取り入れが必要かもしれません。
日本の食文化を活かした腸活の例として、以下のようなメニューが考えられます:
- 朝食: 納豆ご飯、味噌汁、漬物、わかめサラダ。
- 昼食: 玄米のおにぎり、野菜と豆腐の炒め物、昆布スープ。
- 夕食: 焼き魚、根菜の煮物、ごぼうのきんぴら、ヨーグルト。
- 間食: ヨーグルトにチアシードやバナナをトッピング、またはアーモンド。
- 飲酒:飲酒については休肝日を設け、週2‐3回程度少量に控える。できればビールや日本酒などよりウィスキーなどの蒸留酒やワインなどが健康被害は少ないことが報告されている。
結論
腸活は、科学的根拠のある、健康を向上させる有効な方法です。腸内細菌叢の安定は、単なる便通の改善にとどまらず、生活習慣病や精神的な安定にも深く関わっています。食物繊維、プロバイオティクス、プレバイオティクス、バランスの取れた食事、運動、睡眠、ストレス管理を積極的に取り入れ、有害物質を避けることで、腸内環境を整えることができます。日本の伝統的な食文化は、腸活に適した食材や習慣を提供しており、世界的にも注目されています。個々の腸内細菌叢は異なるため、個人に合わせたアプローチも重要です。最新の研究内容を参考に、食生活や自身の生活習慣を見直し、腸活を通じて健康な生活を目指しましょう。
参考文献
- Hou, K., Wu, ZX., Chen, XY. et al. Microbiota in health and diseases. Sig Transduct Target Ther 7, 135 (2022).
- Valdes A M, Walter J, Segal E, Spector T D. Role of the gut microbiota in nutrition and health BMJ 2018; 361 :k2179
- Peirce JM, Alviña K. The role of inflammation and the gut microbiome in depression and anxiety. J Neuro Res. 2019; 97: 1223–1241.
- Slavin, J. Fiber and Prebiotics: Mechanisms and Health Benefits. Nutrients 2013, 5, 1417-1435.
- De Filippis, F., Pellegrini, N., Vannini, L., et al. High-level adherence to a Mediterranean diet beneficially impacts the gut microbiota and associated metabolome. Gut 2016, 65, 1812-1821. リンク
- Benedict, C., Vogel, H., Woting, A., et al. (2016). Acute sleep deprivation reduces gut microbiota diversity in healthy young men. Molecular Metabolism, 5(12), 1175-1186.
- Nishijima, S., Suda, W., Oshima, K., et al. The gut microbiome of healthy Japanese and its microbial and functional uniqueness. DNA Research 2016, 23, 125-133. リンク
- Kato, K., Odamaki, T., Mitsuyama, E., et al. Comprehensive analysis of gut microbiota of a healthy population and covariates affecting microbial variation in two large Japanese cohorts. BMC Microbiology 2021, 21, 142. リンク