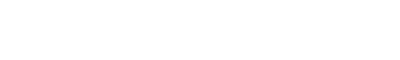2025.09.08
粘液便とは?

目次
「粘液便」とは何か?
粘液便とは、便に腸粘膜から分泌される粘液が肉眼的に明らかに付着・混在している状態を指します。粘液は通常、腸内壁を保護するために分泌されていますが、何らかの異常(炎症・感染・刺激など)で分泌量が増大し、便の表面や周囲に透明、白色、黄色、稀に赤色のゼリー状物質として観察されます。腸は、内部をスムーズに便が通るように粘液を自然に分泌しています。そのため、少量の粘液が便に混じるのは生理的な現象で、必ずしも異常ではありません。しかし、粘液の量が明らかに多い、頻繁に出る、明らかに白い・赤い場合、腹痛や下痢を伴うなどの症状があれば、何らかの病気の徴候である可能性があります。
粘液の役割と作られ方
腸管での粘液は腸管上皮(腸の内側表面)にある杯細胞というによって作られます。その主成分はムチン(mucin)というタンパク質です。
作られたムチンは水分を吸収し、大きく膨潤して粘液層を形成します。この粘液層は「内粘液層(無菌状態)」と「外粘液層(細菌が住む)」の二重で構成されます。
この粘液層は物理的なバリアとして腸内細菌や病原体から腸管を守っています。
食事、腸内細菌、炎症などの刺激によって分泌量が決定されます。また粘液には免疫グロブリンA(IgA)も含まれ、化学的なバリアの機能も果たしています
粘液便が出るメカニズム
腸管は、外敵(細菌・ウイルスなど)や摩擦から粘膜を守るために、粘液を分泌しています。しかし、一定の食事、炎症、刺激、細菌・ウイルス感染が加わると腸粘膜が過敏になり、通常よりも多量の粘液を分泌するようになります。腸内環境も同様に粘液の量に関係していると言われおり、腸内環境の乱れも粘液増加につながります。これらの結果、排便時に目に見えるほどの粘液が便に混ざることがあるのです。
粘液の色や性状は原因によってさまざまで、透明・白色・黄色・赤色の場合、量も便に付着する程度から粘液単独で排出される場合まであります。
粘液便の色と疾患
|
粘液便の色調 |
想定される疾患 |
|---|---|
|
白色 |
下痢の時は腸の粘膜が傷んでいるので、正常の粘液が増加して混じってくることがよくあります。原因として考えられるものは、食あたり、水あたり、消化不良・冷え・ストレスによる下痢です。粘液だけでなく便自体が白い場合は、肝臓や胆管の疾患の可能性があり注意が必要です。 |
|
ピンク色 |
肛門の出口付近にある直腸が傷ついているケースが多いです。便秘で便が硬くなったりすると排泄時に傷がつき、少量の出血と粘液が混じって排泄されます。 |
|
緑色 |
便が緑色になる原因は、酸化した胆汁です。元々、異常がない場合でも胆汁は分泌され便の色を決めています。胆汁の分泌が過剰になったり、小腸や大腸の働きが鈍くなって胆汁の再吸収が行われなくなったりすると、便が緑になる場合があります。基本的に過度な心配は不要です。 |
|
赤色 |
細菌やウイルスにより炎症を起こした腸粘膜や癌から出血していることが考えられます。アメーバといった特殊な感染症でも同様にイチゴジャムのような便が出ることがあります。肛門周囲からの出血でも便が赤くなる場合がありますが、出血が長期間続く時には、大腸内視鏡検査などの精密検査が必要になりますので、粘血便が出た際は早めに医療機関を受診しましょう。 |
粘液便の主な原因と考えられる疾患
粘液便の原因は様々です。以下に主な原因とそれぞれの特徴を表でまとめました。
|
原因疾患・状態 |
特徴的な症状 |
備考 |
|---|---|---|
|
過敏性腸症候群(IBS) |
粘液便、腹痛、膨満感、便秘と下痢を繰り返す |
ストレスや食事内容による消化管運動の変化、腸内環境の変化により粘液が増加し粘液便を認める場合があります。日本人の1割がこの病気とされています。 |
|
感染性腸炎 |
粘液便、下痢、発熱、腹痛、時折血便 |
細菌性(カンピロバクター、サルモネラなど)やウイルス性腸炎、数日単位で症状が改善することが多いですが、一部の細菌・アメーバなどでは長期化する場合があります。 |
|
潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD) |
粘液便、血便、腹痛、下痢、体重減少 |
慢性炎症性腸疾患。再燃と寛解を繰り返す 週~月単位で症状が続きます。粘液便、頻回の下痢、血便が排泄されることがあります |
|
直腸ポリープ・大腸がん |
粘液便、血便、排便習慣の変化 |
病気が進行しないと痛みがない場合も多いですが、ポリープや癌からの粘液・出血が排泄されることがあります |
|
痔・肛門周囲炎 |
粘液便、出血、痛み、残便感 |
肛門周囲の刺激で出血や過剰となった粘液が排泄されることがあります |
|
便秘・排便障害 |
粘液便、硬便、残便感、いきみ |
直腸に粘液が貯まり、貯まった粘液がまとめて排泄され粘液便を認めることがあります |
|
薬剤性腸炎 |
粘液便、血便、下痢 |
鎮痛解熱薬のNSAIDsによる粘膜の傷害、抗生剤による腸内細菌叢の変化などにより粘液増加をきたし粘液便を認めることがあります |
粘液便が続く場合の注意点
一時的な腸の乱れで粘液便が出ることはありますが、以下のような場合には医療機関での精査が必要です。
以下のような場合は専門機関への受診をお勧めします
- 粘液便が何日も続く/繰り返す
- 粘液に血が混ざる、黒い便が出る
- 発熱・激しい腹痛・下痢が伴う
- 食事の摂取が困難
- 体重が急激に減少
- 中高年(40歳以上)で初めての症状
特に、血液が混じる場合は大腸がんや炎症性腸疾患の初発症状の可能性があり、早めの受診が重要です。
粘液便の精密検査;医療機関での診断の流れ
粘液便が続く場合、以下のような検査で原因を調べていきます。
主な検査項目
|
検査内容 |
目的 |
|---|---|
|
問診・診察 |
発症経過や症状の詳細を確認 原因となる病気を絞り込み適切な検査を判断します |
|
便検査 |
細菌感染・ウイルス感染の有無・出血の有無 |
|
血液検査 |
炎症反応・貧血の評価、脱水、電解質の評価 炎症性腸疾患の可能性評価 |
|
腹部エコー |
腸の状態や他の臓器の異常を評価 体内の水分量の評価 |
|
大腸内視鏡検査 (大腸カメラ) |
粘膜の炎症・ポリープ・腫瘍の有無を直接確認 ポリープに関してはその場で治療まで行う場合もあります |
特に40歳以上や、血便を伴う方には大腸カメラの実施が推奨されます。検査によっては、粘膜の一部を採取(生検検査・培養検査)して顕微鏡で原因を詳しく調べることもあります。
治療について
治療は原因疾患に応じて大きく異なります。代表的な治療方針を以下に示します。
|
原因 |
主な治療法 |
|---|---|
|
IBS |
食事改善、ストレスケア、整腸剤、抗不安薬・抗うつ薬 |
|
感染性腸炎 |
対症療法、必要に応じて抗菌薬 |
|
炎症性腸疾患 |
内服薬、注射薬、血液浄化療法など |
|
ポリープ/がん |
ポリープ切除、手術、がんのステージに応じた加療 |
|
痔核・肛門疾患 |
軟膏、座薬、生活習慣指導、必要に応じて外科的治療 |
「粘液便=重大な病気」とは限りませんが、自己判断で市販薬に頼るだけでは根本的な治療にならないことが多いため、専門医の判断が重要です。
日常生活で気をつけたいポイント
粘液便は生活習慣の見直しで改善する場合もあります。
- バランスの良い食事(過度な脂質や香辛料が多い刺激物を避ける)
- 飲酒を控える
- 水分を十分に摂る
- 適度な運動
- ストレスコントロール(睡眠・休息)
- 乳酸菌・水溶性食物繊維の摂取
症状が慢性化している方や、再発を繰り返す方は、食事記録や排便記録をつけると、診察時に役立つ情報となります。
まとめ:粘液便は腸からの重要なメッセージです
粘液便は、腸の炎症や異常を知らせるサインのひとつです。一時的なもの・治療が不要な場合もありますが、症状が長く続く場合や他の症状を伴う場合には、消化器・内視鏡専門の医療機関への受診をおすすめします。
当院では、粘液便や腹部症状に対する丁寧な問診と検査を行い、必要に応じて検査(血液検査、エコー検査、内視鏡検査、便検査)や治療の提案を行っています。
粘液便などの症状がなる方は、どうぞお気軽にご相談ください。