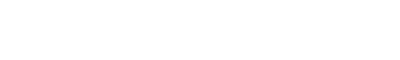診療案内
MEDICAL
- HOME
- 診療案内:血便・下血緊急外来
血便・下血緊急外来
血便・下血緊急外来について
消化器内科医の緊急対応でよく相談があることとして血便があります。よくあるシチュエーションとしてはトイレで便器を見ると真っ赤な鮮血が広がっている場合や、便に血液が付着する場合が多いです。まず言葉の定義で迷ってしまいますが”赤いものが出る”が「血便」で、”黒いものが出る”が「下血」になります。血便や下血を認めた場合は口から肛門までの長い消化管の中のどこかで”血が出ている”ことを意味します。肉眼的にはわからないレベルの出血を同定する検査が便潜血検査になります。血便や下血は内視鏡診療を得意とする消化器内科の守備範囲になります。
血便・下血のタイプ
血便・下血は便の色である程度どこから出血しているかは推測でき、その後の必要な検査の判断材料になります。
鮮血便
鮮やかな赤い血を鮮血便と表現します。つまり出血して時間が経過していない血になります。よく”便に血が付着する”や”トイレットペーパーに血が付く”などと表現されます。お尻(肛門)の痛みを伴うこともあり、その際は肛門出血(痔など)が疑われます。出血の原因としては切れ痔、痔核(内痔核と外痔核)などからの肛門出血、直腸がん、潰瘍性大腸炎などの肛門に近い部位からの大腸の出血が考えられます。また大腸憩室出血で出血量が多い場合は深部の大腸からの出血であっても鮮血便を認めます。
暗赤色便
大腸や一部小腸からの出血が考えられます。特に腹痛を伴う出血かで考えられる疾患が変わってきます。腹痛を伴わない暗赤色便であれば大腸がんや大腸憩室出血などが考えられます。腹痛を伴う暗赤色便であれば右側の腹痛であれば感染性腸炎(カンピロバクターなど)による出血、左側の腹痛があれば虚血性腸炎による出血、部位の関係のない腹痛を伴う出血であれば潰瘍性大腸炎やクローン病などが典型です。
黒色便(タール便)・下血
血液は出血して時間が経過すると酸化され赤から黒色に変化します。黒色の便、特にタール便と呼ばれるコールタール(石炭を高温乾留する際に生成される油状物質)に類似しているドロッとした真っ黒な便で独特な血生臭い匂い便の場合は、胃や十二指腸からの出血を考えます。この黒色便を下血と表現します。出血の原因としては胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がん、食道がん、十二指腸がんなどが考えられます。
便潜血検査陽性
非常に微量の出血を同定する検査で、肉眼でわかる血便や下血がある場合には用いることはありません。便潜血検査は大腸がん検診に用いられる検査ですので、陽性の場合は積極的に大腸内視鏡を受けていただくことをお勧めします。
血便のタイプが判断つかない場合は是非写真を撮って、受診時に医師に提示してください。専門医が適切に判断いたします。
疾患について
痔(内/外痔核、切れ痔)
痔は血便の一般的な原因の1つです。痔核は直腸周囲の静脈が腫れることによって生じる症状であり、しばしば直腸内や直腸の周りにかゆみ、疼痛、出血などの症状を引き起こします。また肛門の表面が切れる切れ痔でも出血の原因となります。
大腸がん/直腸がん
血便を認める際に、消化器の専門医が最も考え、最も否定しておきたい病気が大腸がんです。大腸がんと直腸がんは、大腸や直腸の組織で発生するがんの一種です。大腸がんは、ポリープ(腺腫)が悪性になった腫瘍がほとんどを占めます。腫瘍が潰瘍を形成し出血することで血便の原因となります。
虚血性腸炎
虚血性腸炎は、腸管内の血液供給が不足していることにより、腸管組織に障害が生じる疾患です。この状態は通常、腸管の血流が一時的または一時的に低下したり、遮断されたりすることによって引き起こされます。好発年齢は60歳以上の女性ですが、若年で発症することもあります。背景に便秘や動脈硬化があることとされています。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の内膜に炎症や潰瘍(ただれ)が起こる疾患です。潰瘍性大腸炎は炎症性腸疾患(IBD)の一種であり、クローン病と並んで主要なIBDの一つと見なされています。基本的に血便は長期間(月単位)続く慢性疾患です。
感染性腸炎
感染性腸炎は、細菌、ウイルス、寄生虫などの病原体が消化管に感染し、腸の炎症を引き起こす疾患の総称です。血便の原因となる感染性腸炎は細菌や細菌の産生する毒素による腸炎になります。
大腸憩室出血
大腸憩室出血は、大腸に存在する憩室と呼ばれる袋状の突出部分から出血が起こる状態を指します。憩室は通常、大腸の壁に存在する自然な構造であり、一般的には症状を引き起こしません。しかし、憩室に存在する直動脈という血管が破綻することで出血を起こし血便の原因となります。緊急の止血処置が必要になる場合があります。
検査について
血便や下血といっても、出血の量は患者さんそれぞれで違います。常に鮮血便が出続ける状況からトイレットペーパーに血が付着するまで程度は様々です。まずは問診や便の写真から出血の緊急性を判断します。その上で以下のような検査を行います。
血液検査(血球検査、生化学検査)
出血の量が多いと想定される場合は血液検査で貧血の状況を確認します。また生化学検査の項目であるBUN(尿素窒素)とクレアチニンの検査値の比率で胃や十二指腸からの出血なのかの判断の目安になります。
当院ではこれらの血球検査・生化学検査は全て院内で15分以内に測定可能です。緊急性の判断なども迅速に行うことが可能です。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
出血原因を直接観察できる検査になります。大腸がんであれば組織を採取し診断が可能になります。鮮血便や暗赤色便であれば大腸からの出血の可能性高いため、大腸内視鏡で大腸の精査を行います。ただし、大腸憩室出血の場合は憩室が多発することが多く、出血源の憩室の特定ができない場合もあります。
胃内視鏡検査(胃カメラ)
特に黒色便の場合や大腸内視鏡検査で異常がない場合に胃内視鏡検査が行われることがあります。十二指腸潰瘍で出血量が多い場合は”血便”として見つかることもあるため、胃内視鏡検査はたとえ血便の場合でも診断的に必要な場合があります。
カプセル内視鏡(当院では実施しておりません)
小腸は口からも肛門からも遠い消化管になり、胃内視鏡と大腸内視鏡では基本観察できません。そこでカプセル状のカメラを飲み込んで、消化管内の写真を解析することで出血源の同定に役に立つことがあります。撮影される枚数は通常5万枚から10万枚程度になり、専門医が読影します。
造影CT(当院では実施しておりません)
造影剤を使用するCT検査では、血管の流れに沿って造影剤が分布するため消化管内部に造影剤が漏出することがあります。これをExtravasation(血管外漏出)と呼びます。この所見を認めたらその部位から出血していることを示唆します。このCTの情報をもとに大腸内視鏡や胃内視鏡検査の方向性を決定します。
まとめ
血便・下血は量が多ければ緊急性のある症状です。また出血量が少しでも放置していい血便・下血はありません。当院では血便や下血の訴えがある場合は優先して対応いたします。